

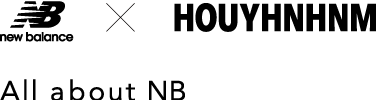

- FEATURE
“1000点満点で、990点”。〈ニューバランス〉990をあらわす有名なキャッチコピーです。「990」が生まれたのは1982年。時間と費用に妥協せず、技術的に可能な限り最高のランニングシューズを開発するという、いわば当時の力を結集して生み出されたマスターピースなのです。時代の変化のなかでその基準を常に上方修正し続け、2019年4月末には、現時点の「990点」であるV5がリリースされました。ランドスケーププロダクツから独立後、設計事務所スタジオドーナツを北畑裕未さんと主宰する鈴木恵太さんは、設計とインテリアデザインという生業を通じて、建築、インテリア、調度品など、多くの名作にふれてきました。タイムレスなプロダクトの価値を知るデザイナーの視点から浮かび上がる、〈ニューバランス〉と「990」の魅力とは?
茨城県笠間市出身。工業系の大学に通っていたが、もともと好きだったデザインを学ぶため桑沢デザイン研究所へ。卒業後、(有)ランドスケーププロダクツに入社し、自社ブランドの企画やデザイン、営業まで多岐に渡って担当。2015 年よりSTUDIO DOUGHNUTS として活動し、「FOOD&COMPANY」(学芸大学)、「archipelago」(丹波篠山)、「YOUNG」(下北沢)、「SAN」(大阪桜川)などの店舗やリノベーション物件などを手がける。
instagram.com/studio_doughnuts



ニューバランスのブランドイメージについて、どんな印象がありますか?
鈴木マイナーチェンジを続けてデザインを更新しているブランドだと思います。あまり奇をてらったことをしないで、基本となっているモデルのデザインを大事にしているなと。枠から逸脱しないというか、新しい素材や技術を取り入れているのにトラディションが崩れていない。そのイズムみたいなものは、この「990v5」からも感じますね。もうひとつは、要所要所で良いコラボレーションに取り組んでいるなということ。僕は〈ニューバランス〉の靴を二足持っているんですけど、二つともコラボレーションモデルなんです。〈マーガレットハウエル〉との「420」は結婚祝いにプレゼントしてもらったもので、〈J.クルー〉との「1400」はどうしても欲しくて海外通販しました。なので、通常モデルを履いたのは、実は今回がはじめてなんですよね。

990v5 ¥28,000+TAX
そうだったんですね。今回は「990 v5」でランニングも試してもらいました。どうでしたか?「990」は元々、ランニングシューズとして開発されているんです。
鈴木街で履いている人が多いモデルというイメージだったけど、ランニングでもまったく問題ないですね。特に驚いたのは、地面に着地した時の安定感がしっかりしていて。

ランニングはいつから始めているんですか?
鈴木3年前くらいですね。僕らのアトリエを兼ねた住まいは、都内にあるとはいえ郊外寄りの立地なので、同じ東京といえど生活スタイルがまったく異なるんです。車社会のエリアということに加えて仕事柄、車を運転しなければいけないことが多いので、車移動が中心だとどうしても運動不足になってしまうんですね。だから、運動不足を解消するためにランニングを本気で始めました。ランニングは純粋に気持ちいいですし、ひとりで黙々とタイムを意識しながら走るのが好きです。子どもが生まれてからは以前ほど走れていないけど、一時期は一ヶ月で200kmくらい走っていましたね。
月間200kmって結構な距離じゃないですか!
鈴木僕らが生業としている内装設計やインテリアデザインは、毎日達成感を感じられる仕事ではないんですよ。小さな達成感が日々あると、テンションが上がるじゃないですか。だから、毎日コツコツと10キロ積み上げていくのが、とにかく楽しくて。

デザイン面の感想も聞かせてください。空間の設計や店舗の内装を手がける身としては、990v5の特徴をどう捉えましたか?
鈴木グレーのワントーンの明度とテクスチャーの違いを組み合わせつつ、プロダクトとしてすごくまとまっていますよね。フラッグシップモデルのひとつだということも頷けますし、このデザインの組み立て方は、僕らと近しいものを感じます。
スタジオドーナツの屋号には、「二重丸、身近な存在でありたい」という意味が込められていますよね。「990」には「1000点満点で、990点」というキャッチコピーがあるんですが、ここには二重丸や身近な存在というニュアンスもあるように感じていて。他に思い当たる共通項はありますか?
鈴木奇抜なアイデアやカラーを使わず、パッと目を引くためのデザインを選択しない、という部分ですかね。僕らはカジュアルで身近な空間づくりを常に意識していて。そこで過ごす人たちに異世界や特別な体験を味わってほしいわけではないんです。それを実現するために、建物が秘めているポテンシャルを引き出せるデザインを心がけています。床・壁・天井を全部ピカピカにつくるよりも、元々ある素材を生かしながらデザインしていく。それがスタジオドーナツの持ち味なのかなと。


―「FOOD&COMPANY」(学芸大学)、「archipelago」(丹波篠山)、「YOUNG」(下北沢)、「SAN」(大阪桜川)など、スタジオドーナツが設計した店舗は、スタイリッシュな雰囲気の中にも適度なアナログ感があると思います。そのバランスのとれたハイブリッド感は「990v5」との共通項なんじゃないかなと。
鈴木そういう意味では、僕らは内装設計と同時にインテリアデザインもやっているんですよね。スツール、傘立て、トイレットペーパーホルダーとか、既製品を使わずに特注で家具をつくることで空間を差別化できるんです。こういうものがあったらいいなと、自分たちで定番化するという意識でやっています。

「990」は伝統と最新テクノロジーを融合させて、アップデートを繰り返してきました。流行に左右されない普遍的なプロダクトって、建築やインテリアの分野にもたくさんありますが、いわゆる名作の魅力をどう捉えていますか?
鈴木時代を超えても愛される、ということじゃないですか。ランニングシューズはリペアして履き続けるのは難しいけど、僕は気に入ったものに出会えたら、それを使い続ける性格なんです。靴に限らず、基本的には名作と評価されるものと過ごしたいんですね。
たとえば、スタジオドーナツのアトリエ内にはそういったものはありますか?

P-CASE
鈴木いろいろありますよ。これなんかはAppleのデザイナーだった西堀晋さんが、パナソニックに在籍していた頃にデザインした「P-CASE」というCDラジカセです。リピート機能が付いていなくて現代では使いづらいけど、シンプルなデザインと、なぜか無印良品から製品化されているという部分も気に入っていて。
所有しているだけで、生活の質を高めてくれる雰囲気がありますね。
鈴木そうなんです、だから手放せないっていう(笑)。上質感を意識してデザインされているプロダクトというのは、990にも当てはまると思います。ライフスタイルプロダクトいうか。ファッションとして誰かに見せるのではなく、生活の質を高めるという観点で選ぶ人が多いのかもしれませんね。
たしかに、その観点は多いと思います。他にはどんなものがありますか?

AW-1
鈴木オーディオつながりだと、BOSEのAW-1もそうですね。これは父親から譲り受けたラジカセで1980年代に購入しているので、親の代から30年以上使っていることになります。
初代「990」が1982年にデビューしているので、同じくらいの歴史がありますね。
鈴木AW-1を趣味でオーバーホールしている方をネットで見つけて、傷んでいた部分を直してもらったんですよ。ラジカセの機能以外に、レコードプレイヤーとカセットプレイヤーとつないで聴けるスピーカーとしても使っていて。もう一つは、ボーエ・モーエンセンがデザインしたシェーカーチェアですね。座面のペーパーコードが特徴的なデザインは、当時からしたら画期的だったと思います。これはゴミ捨て場で偶然見つけて救出したものなので、リプロダクトかもしれないですけど。

ボーエ・モーエンセンがデザインしたシェーカーチェア
どれも時代を超えて愛されているものばかりですね。そういった名作に囲まれながら生活するなかで、仕事にフィードバックされている要素って何でしょうか。
鈴木僕らがデザインする空間やインテリアも、こういった名作のように長く愛されてほしい、という気持ちが強くなりますよね。時代を超えるということは、ものすごくハードルが高いことだと思っていて。愛着を感じられる部分がなければ簡単に捨てられてしまうし、愛しやすいデザインってなんだろうなって考えるようになりました。僕らが設計したお店も、デザインしたインテリアも、まだ完成してから10年も経っていないんですよ。そう考えると、30年以上もアップデートを繰り返している990はすごいなって憧れます。

手がけたお店やインテリアが30,40年後にどうなっていてほしいですか?
鈴木極論を言えば、僕らがデザインしたという事実は忘れられてもよくて。日常に溶け込む場所やモノとして、多くの人たちの生活にとって、僕らの屋号に込めた“身近な存在”であってほしいですね。